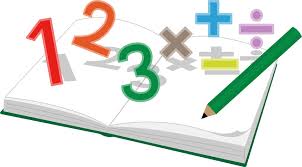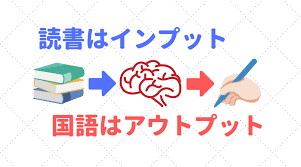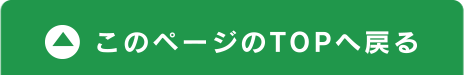昨日と今日が、三次考査の「集中日」でした。
9月18日から対策授業を開始し、土・日・月の福祉公民館での勉強会を含め、毎日、各自のテスト範囲の問題演習を繰り返してきました。
今回は、社会を中心に用語を覚えるのに苦労していた塾生が多く見られました。
まず、長い用語です。
今回のテスト範囲で言えば、「男女雇用機会均等法」「男女共同参画社会基本法」「連合国軍最高司令官総司令部」(中3)などです。
これは、結局は繰り返し口で唱えて手で書いて、口と手に覚えこませるしかありません。
ただ、闇雲に繰り返してもなかなか覚えられないので、塾生には文字数を意識するように指導しています。
「連合国軍最高司令官総司令部」であれば、「連合国軍+最高司令官+総司令部」なので、「4+5+4」というイメージを持っておくと、覚えやすくなります。
たったこれだけのことですが、教えないと意識せずにただ繰り返して書いているだけというケースが意外に多いようです。
また、「アジア太平洋経済協力会議(APEC)」の場合、Aはアジア(Asia)、Pは太平洋(Pacific)の頭文字だということを知らずに「覚えられない」と言って悩んでいる塾生が意外にたくさんいました。
これも見つけしだい指摘しています。
英語が得意な塾生には、英語(Asia-Pacific Economic Cooperation)も調べてセットで覚えさせます。
「枕草子―清少納言」「源氏物語―紫式部」、の組み合わせが覚えられない中1の塾生には、「足して7文字になるように」と教えました。
塾生はこれでわかったと言ってくれました。
文字数で覚えるというのはかなり使えると思っています。
鎌倉六仏教(浄土宗―法然、浄土真宗―親鸞、時宗―一遍、日蓮宗―日蓮、臨済宗―栄西、曹洞宗―道元)はそのまま覚えるのがベストですが、覚えられない場合はネットから拾った語呂合わせで覚えさせています。
そのあとで、必ず筆記のテストをして、漢字の間違いがないかを確認しています。
中2では、「生類憐みの令」や「公事方御定書」などの読み方を調べずにただ繰り返して覚えようとしている塾生がいました。
やはり、正しい読みとセットでないと覚える効率が悪くなり、意味も頭に入りません。
また、「御」の漢字の間違いが非常に多く、「御」を書いている塾生がいたら、必ずチェックすることにしています。
文字数や語呂合わせなど、ひと工夫することで用語の組み合わせは覚えやすくなりますが、いちいち自分でそれを考えながらだと、テスト対策では時間が足りません。
「覚えられない」という相談があったときは、同じテスト範囲の塾生にまとめて、覚えるためのひと工夫を伝えるようにしています。
勉強のやりかたも含めて、一度教えたはずのことが定着していないことがあります。
常に塾生の反応を確認し、覚えていないこと、忘れていることがないか、掘り起こしながら知識の定着を図っていきたいと思います。
画像は、福祉公民館の窓から。塾生が空の色が綺麗だと言ったので。